|
|
(A)事業譲渡清算型のスキーム等においてタックス・プラニングがより重要になってくる。 |
●清算所得課税改正に伴う倒産会社に関する取扱い
法的整理を申し立てるような会社では、粉飾決算に伴う架空資産(架空の売掛金や在庫等)や過去から引きずっている内容の分からない資産があったりするものです。これらは、単純に損金処理ができるものではなく、清算所得課税の
廃止が明らかになった段階では実務家の間でその処理が懸念事項でした。
その後、これらの「実在性のない資産」についての取扱いが国税庁から公表されました。すなわち、①更正の対象期間(7年間)内
に生じたものについては税務当局による更正手続きを通じて遡って損金処理し、②それ以外(7年以上前もしくは時期が不明)の場合には税務上の剰余金(欠損金)の期首繰越金額を直接修正する、というものです
。なお、繰越額を直接修正できるのは、法的整理など損失処理の手続きに客観性が担保されている場合に限られます。
このように、「実在性のない資産」の処理に関して制度としては手当がされたものの、現実の運用としては悩ましいところです。というのは、更正の手続きは納税者側が当該資産が架空であることを立証して、当局にそれを認めてもらう必要があり、その立証には困難を伴うこともあるからです。
●清算所得課税に注意が必要な会社
上述のように多額の架空資産があって、その疎明が難しい場合には免除益課税回避にとって障害となります(上記取扱いの趣旨からすれば、更正手続きに当局の柔軟な運用が期待されるところです)。このほかにも、清算所得課税
(債務免除益課税)で注意が必要なパターンをいくつか挙げると次のとおりです。
①資本金の小さい会社
清算所得の申告において債務免除益課税が生じてしまうのは、会計上の損失のうち税務上は損金として処理できなかった部分(以下、「否認部分」といいます)が発生するからです。
この否認部分はどのケースでも発生しうるのですが、直ちに免除益課税に結びつくものではありません。なぜなら、少なくとも会計上は、残余財産確定時には債務免除益を上回る欠損が
必ず生じ
ているからです。したがって、否認部分の金額がその差額(会計上の欠損金が債務免除益を上回る差額)に納まるかぎり、税務上も欠損金額が債務免除額を上回り、課税は生じません。
この、会計上の欠損金が債務免除益を上回る差額(以下、「欠損余裕額」といいます)というのは、下図のとおり資本金(払込資本)の金額に相当します。ですから、資本金が厚ければ否認部分が生じてもこれを吸収することができます。下図で否認部分が30のとき、資本金
が小さい10のケースでは20(否認部分30-欠損余裕額10)の清算所得が生じますが、資本金が大きい50のケースでは課税は生じません(否認部分30-欠損余裕額50=△20)。
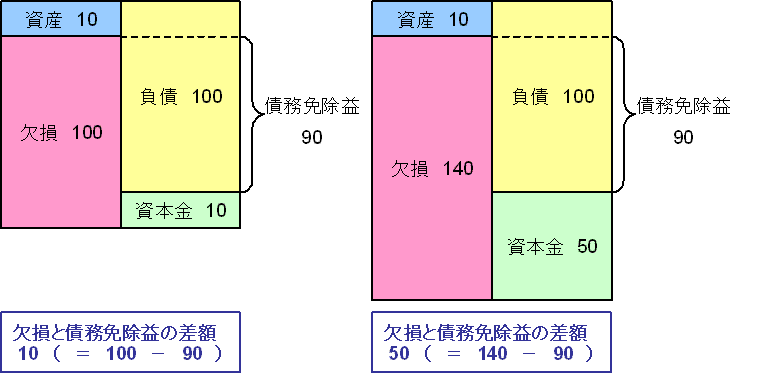
逆の言い方をすれば、資本金の小さな会社では否認部分を吸収するクッションが小さいため、債務免除益課税への注意が必要になります。
②多額の役員貸付金がある会社
オーナー会社では、役員に対する貸付金や仮払金等の債権が多額に計上されているケースがあります。役員に対する債権は回収見込みがないからといってうかつに債権放棄で処理すれば、役員に対する利益供与として役員賞与として認定されます。この場合、損金処理できないばかりか、個人の給与所得として源泉所得税の納付義務が会社側に生じます。。
税務リスクを回避するためには、役員個人の破産手続きを受けて貸倒処理するのが確実です。実務上、代表取締役は連帯保証の関係もあって個人の手続きも行なうでしょう
。しかしながら、連帯保証をしていない役員は破産手続きをしないことも考えられ、この場合には税務リスクが生じます。
清算所得課税の改正によって、これまで曖昧に処理できた項目も手順を踏みながら処理していくことを求められるようになり、これまで以上にタックス・プランニングが
重要になってきました。
なお、これまで破産事件では実務上、税務申告を行なわないケースが散見されました。しかし、清算所得課税の改正により、建前としては税務申告をしないと免除益課税が生じる場合もあり(期限切れ欠損金を利用する場合の特例適用は申告が要件)、注意が必要です。
■
|